はじめに
資格取得を考えたときに、よく候補に上がるのが「FP(ファイナンシャル・プランナー)3級」です。
リベ大の両学長もおすすめしていて、私自身も2025年10月19日に受験を控えて、今まさに勉強中です。
ただ実際に勉強を始めてみると、テキストや問題集の分厚さ、出題範囲の広さに圧倒されました。
「こんなに分野があるの?」「暗記することが多すぎる!」と何度も心が折れそうになったのが正直なところです。
そこでこの記事では、FP3級を取る前に知っておきたかった20のこと を、勉強中のリアルな気づきも交えてまとめました。
これから受験を考えている方が「最初に知っておくと安心できるポイント」をお伝えしていきます。
試験概要を知っておこう

FP3級を受ける前に、まずは全体像を押さえておくことが大切です。
試験の仕組みや出題分野を知っておくだけで、勉強の見通しがぐっと立てやすくなります。
出題範囲はとにかく広い
FP3級では、「ライフプランニング」「保険」「年金」「不動産」「税金」「金融資産運用」など、暮らしに関わる幅広い分野が問われます。
1つひとつの分野はそこまで深くありませんが、全体をカバーしようとすると想像以上の広さに圧倒されるはずです。
最初から「全部完璧に覚えよう」と思わず、「よく出る分野から優先的に学ぶ」意識が大切になります。
合格率は高め、でも油断は禁物
FP3級の合格率は例年60〜70%前後と高めです。
「簡単そう」と思うかもしれませんが、油断は禁物です。
出題範囲を甘く見て手を抜いてしまうと、不合格になるケースも珍しくありません。
過去問の繰り返しが必須
FP試験は「過去問からの出題率が高い」ことでも有名です。
同じ形式・同じ数字が出題されることもあり、過去問を解かずに本番に臨むのはおすすめできません。
最初は難しくても、繰り返すうちに「またこのパターンだ」と気づけるようになり、得点源にできます。
勉強を始める前に理解しておくべきこと
FP3級の勉強を始めるとき、最初につまずきやすいのが「教材の選び方」と「勉強スタイル」です。
ここを押さえておくと、無駄な時間や不安を減らすことができます。
教材は分厚い! → 配分が大事
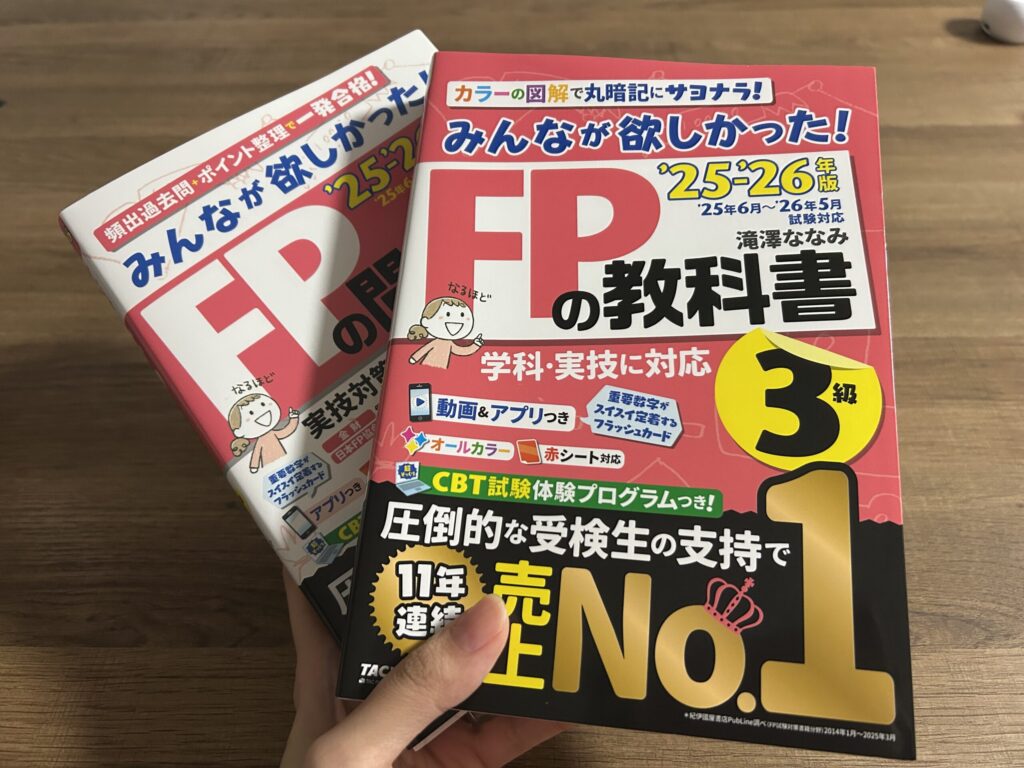
市販のテキストや問題集は、とにかく分厚くボリュームがあります。
私も「みんなが欲しかった!FP3級」シリーズを手に取ったとき、その厚さに正直びっくりしました。
最初から最後まで完璧にやろうとすると途中で挫折しかねません。「テキストはインプット用に流し読み」「問題集を繰り返して定着」と役割を分けると続けやすいです。
「みん欲」+動画学習の組み合わせが強い
独学の場合は「テキスト+問題集」の組み合わせで十分対応可能です。
特に「みんなが欲しかった!」シリーズは、図解が多く初心者でも理解しやすいのが魅力です。
さらに私の場合は、YouTubeの「ほんださん FP3級爆速講義」を活用しています。
耳から聞くことで理解がスムーズになり、移動中や家事の合間でも勉強できるので効率がアップしました。
通信講座という選択肢もある
独学が不安な人や、勉強スケジュールを立てるのが苦手な人は、通信講座を利用するのも一つの手です。教材が体系的にまとまっていて、添削や質問サポートも受けられるので安心感があります。
ただし費用は独学より高くなるため、自分の性格や生活スタイルに合うかどうかで選ぶと失敗しにくいです。
勉強スケジュールの立て方
FP3級は範囲が広いので、行き当たりばったりで勉強すると途中で混乱してしまいます。
最初に「どのくらい勉強時間が必要か」「どんな順番で進めるか」を知っておくと安心です。
勉強時間の目安

一般的にFP3級の合格に必要な勉強時間は 50〜100時間程度 といわれています。
毎日2時間しっかり確保できる人なら1か月、仕事や家庭と両立する人なら2〜3か月を目安に考えると現実的です。
通信講座サイトでは、あくまで試験に合格するための勉強であれば、20時間程度でも可能という記載もありました。
3か月前〜試験直前までの流れ
- 3か月前:テキストで全体像をつかむ
分厚い教材を最初から理解しようとせず、ざっと流し読みして「どんな分野があるのか」を把握する。 - 2か月前:問題集を繰り返す
最初は解けなくてもOK。答えを見ながら進めて「出題のされ方」に慣れる。
2周目からは「同じ問題は必ず正解する」意識を持つ。 - 1か月前:過去問演習を中心に
本番と同じ時間を測って解いてみる。
間違えたところはテキストに戻って復習し、弱点を補強する。 - 直前期:弱点つぶし&数字の暗記
特に税金や保険の数字問題は直前にもう一度叩き込む。
軽く全体を見直しながら、自信を持って試験に臨む。
過去問は何周すればいい?
FP3級は「過去問からの出題率が非常に高い」資格です。
最低でも 3回分(3年分)を2〜3周 はしておきたいところ。
解けば解くほど「同じパターン」が見えてくるので、確実に点数につながります。
継続のコツ
FP3級の勉強で一番大切なのは「継続」です。
範囲が広いからこそ、勉強を止めてしまうと再開が大変になります。
忙しい社会人でも続けられるコツをまとめました。
忙しくても続けられる工夫
- スキマ時間を使う
通勤・昼休み・家事の合間に「1問だけ」「10分だけ動画を見る」でも十分。
机に向かえない日があっても“ゼロの日”を作らないことが大切です。 - 耳からインプット
YouTubeの「ほんださん爆速講義」などを流し聞き。
移動中や家事をしながらでも知識が定着します。 - 机に向かえるときはアウトプット優先
落ち着いて勉強できる時間は「問題演習」「過去問」に集中。
インプットよりもアウトプットを重視した方が効率的です。 - 毎日1ページでも触れる
「今日は忙しいから1ページだけ」「1分だけ」と小さなハードルにすると継続しやすいです。 - 環境を変えて気分転換
カフェや図書館など、場所を変えるだけでも集中力が回復します。
試験当日までに準備しておきたいこと
FP3級は現在、すべてCBT(パソコン受験)方式で実施されています。
紙試験とルールが大きく違うので、事前に確認しておくと安心です。
会場に持ち込めないもの
筆記用具、電卓、腕時計、スマートフォン、参考書など、私物はすべて持ち込み禁止です。
会場に入る前にロッカーに預けることになります。
会場で用意されるもの
試験中に使うメモ用紙や筆記具は会場から貸与されます。
計算は自分の電卓ではなく、試験画面上に表示される電卓機能を使います。
普段の電卓と操作感が違うので、事前に手計算で練習しておくと安心です。
当日に必要な持ち物
CBT方式では従来の「受験票」は不要で、顔写真付きの身分証明書が必須です。
運転免許証やマイナンバーカードなどを忘れずに持参しましょう。
当日の流れと注意点
試験会場には開始30分前には到着するのが安心です。
直前は新しい範囲に手を出さず、過去問でよく出る分野や数字の確認に時間をあてると落ち着いて臨めます。
まとめ

FP3級は、生活に役立つ幅広い知識が学べる資格です。
ただ、出題範囲の広さや教材の分厚さに最初は圧倒されがちです。
今回紹介した「取る前に知っておきたい20のこと」を押さえておけば、勉強の見通しが立ちやすくなり、効率よく学習を進められます。
特に、スキマ時間を活用して毎日少しずつでもFPに触れることが、合格への一番の近道です。
私自身も2025年10月に受験を控えており、今まさに勉強の真っ最中です。
この記事が、これから受験する方の不安を少しでも軽くし、「自分も挑戦してみよう」と思えるきっかけになれば嬉しいです。
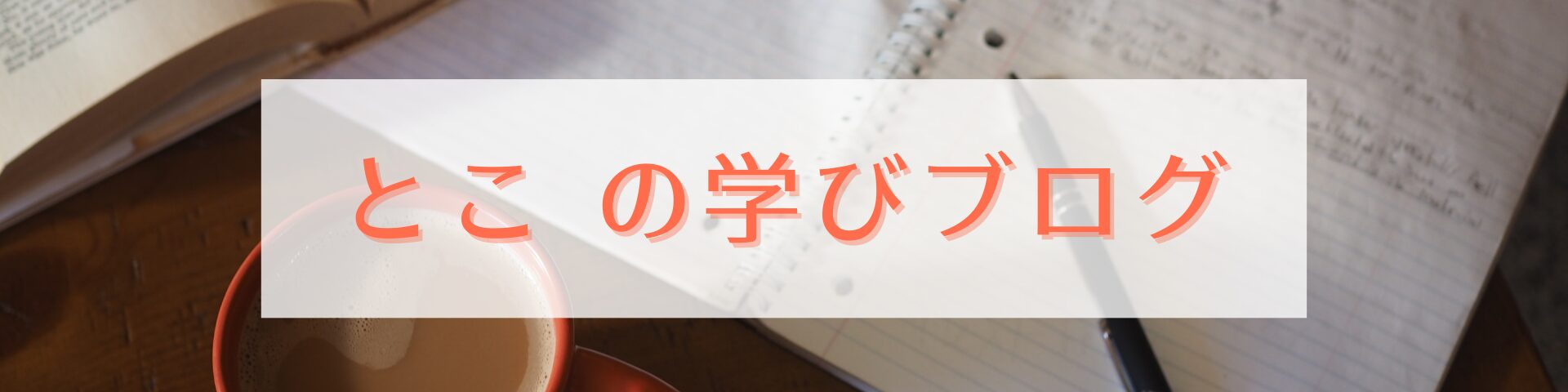
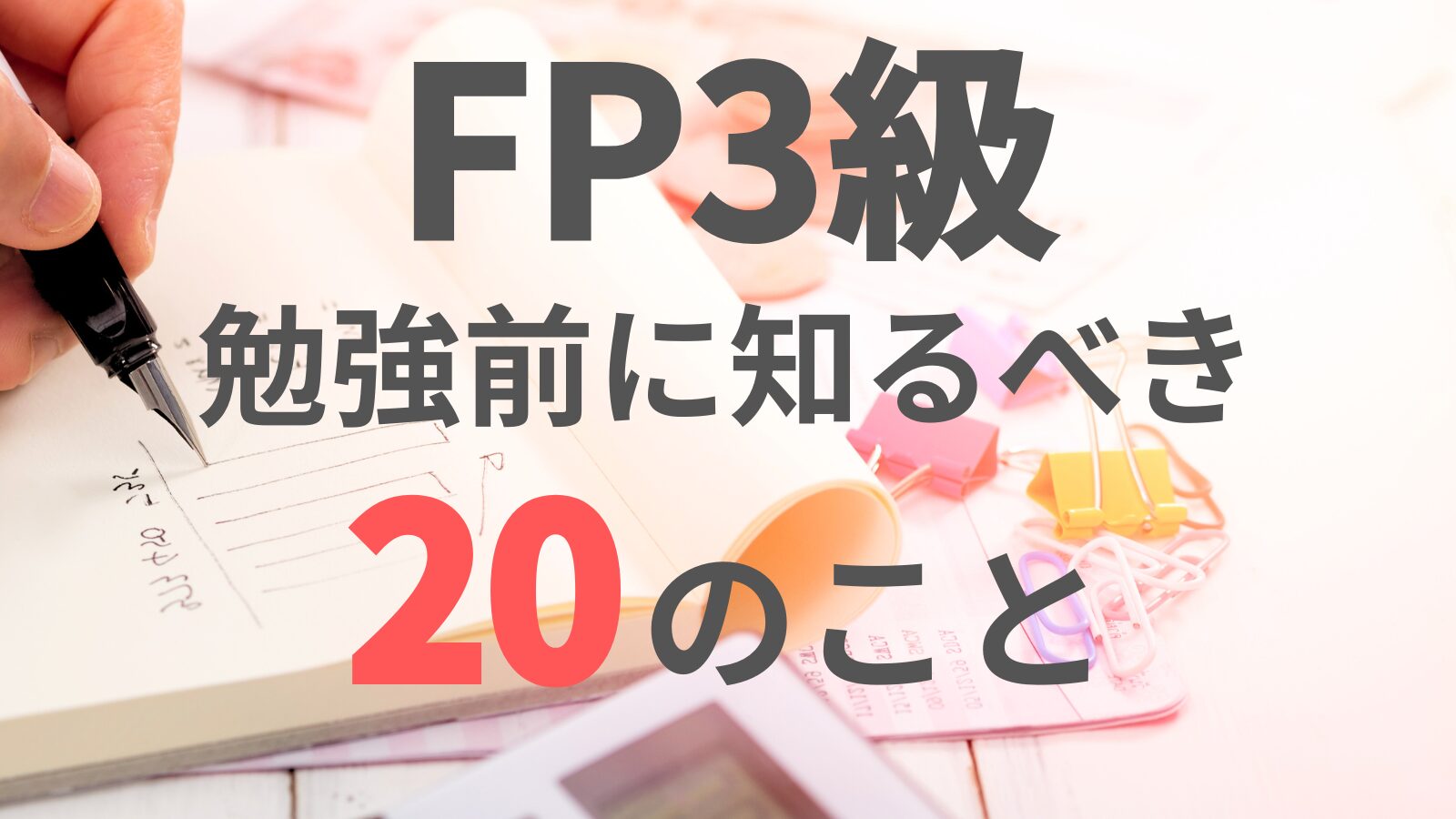
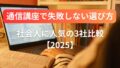

コメント